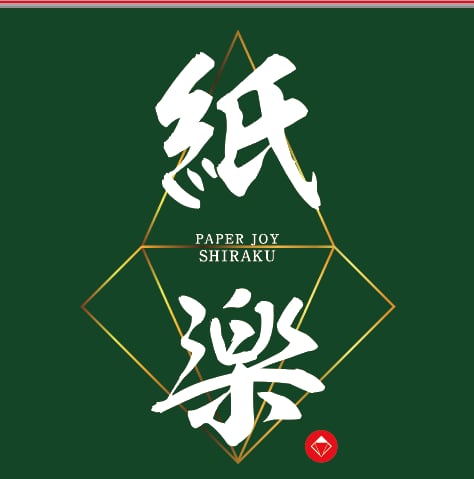2025/02/08 20:13
紙という漢字の語源について、興味深い情報を見つけましたのでご紹介します。
紙は中国がその発祥の地であり、その成立は紀元前30年から124年にかけて活躍した許慎の辞書「説文解字」(西暦100年)に初めて見られます。説文解字によると、「紙絮一苫也」(紙は絮の一苫なり)と記されており、紙は「絮(じょ)を洗って、簀(す)でこしたもの」とのことです。絮(じょ)とは古真綿のことで、その懸濁液を簀(す)で漉き取り、簀の上に残った薄い繊維を乾かしてできたものが紙だったのです。
紙の漢字は、「糸」の偏(へん)と「氏」の旁(つくり)から成り立っています。「糸」は蚕糸を撚り合わせた形を示す象形文字であり、「氏」は匙(さじ)の形を描く象形文字で滑らかさを表します。このように、「糸+氏=紙」が蚕糸を匙のように薄く平らに漉いた、柔らかいものを意味します。
紙の読み方について、かつては簡(かん=木簡、竹簡)という書写材料が使われていました。その字音である「カン」が次第に「カニ」「カミ」と変化したと考えられています。日本語としての「カミ」の発音は奈良時代から使われるようになったとされ、その語源には諸説があります。竹簡や木簡の「簡」(カン、カヌ)からカミに転韻したとの説や、樺(かば)の木の樹皮に書かれたことからカバ→カビ→カミに変化したとの説などがあります。また、音読みである「し、シ[shi]」は中国語の紙 [zhi](ジイ)より来たもののようです。
紙の読みには、「神」「上」「帋」「守」など、高貴なイメージがあります。これは学問的な見解とは別に、紙が古くから大切に扱われてきた歴史や、繊細で美しいものとしての特性によるものかもしれませんね。
紙は日常生活に欠かせない素晴らしい素材であり、その語源にも魅力的な背景があることが分かりました。紙の歴史や文化を大切にし、さらなる発展を願いたいと思います。
おわり